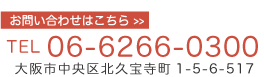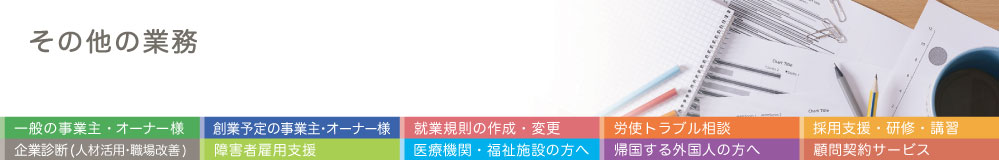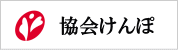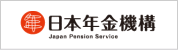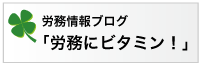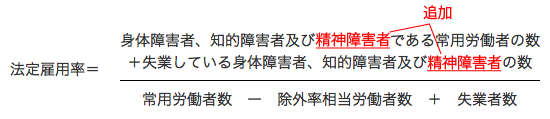企業診断(人材活用・職場改善)
■ 人材活用・職場改善のための企業診断 [ 無料 ]
企業診断システムは、高齢労働力の活用に向けて企業内において取り組むべき課題と方向性を整理するために開発されたシステムです。
- 貴社が求める能力を明らかにします。
- 今後重点を置くべき能力開発について診断します。
1、 教育訓練診断
高齢化に対応した企業内教育の実施度合いと必要度、「どんな能力を必要としているのか」の現状を把握し、検討・工夫すべき問題点が明らかになります。
- 職場における照度・騒音・室温・レイアウトなど作業環境の現状と問題点について診断します。
- 職場における作業条件の現状と問題点について診断します。
2、職場改善診断
企業における職場環境等の現状をチェックし、仕事の仕方や職場環境を改善し、過度の負担をなくして生産性を高めることによって、高齢者を戦力として活用するためのヒントを得ていただけます。
- 健康管理体制の整備状況について診断します。
- 従業員への疲労対策、過重労働対策の実施状況について診断します。
- メンタルヘルス・ケアの体制づくりについて診断します。
3、健康管理診断
年齢にかかわらず、多くの従業員は適切な健康管理上の配慮がなされればいつまでも戦力として働くことができます。「従業員の健康維持・増進のため、どのように企業として必要な体制を整備するべきか」を整理し、検討すべき問題点が明らかになります。
4、雇用力把握診断
④期待する役割 ⑤評価・処遇 ⑥活用の推進体制
の6つの要素からどのような人事管理上のポイントを重点的に検討、推進すればよいか、また、そのために必要な条件整備としてどのようなものが求められているのかを考えるヒントを見出します。
-
お申込み・詳細は
または
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 大阪支部 TEL 06-7664-0782
へお問い合わせください。
障害者雇用支援
■ 障害者を雇用することのメリット
- 個々の特性によっては健常者以上の働きが期待できる
- 個々の障害特性に合わせた職務内容を検討し、訓練によって健常者以上の作業効率を生み出すことも可能である。
- すぐに辞めてしまう健常者よりも経済効率が良い
■近年の主な法改正による障害者の雇用対策
| 2009年4月~ | 障害者雇用納付金制度において、特例子会社のほか、企業グループ、事業協同組合で適用できる特例を創設 |
| 2010年7月~ | 障害者雇用納付金制度が適用される対象範囲を、常用労働者200人を超える中小企業に拡大。カウントされる雇用障害者に短時間労働者を追加 |
| 2013年4月~ | 障害者の法定雇用率を引上げ(民間企業においては現行の1.8%から2.0%に) |
| 2015年4月~ | 障害者雇用納付金制度が適用される対象範囲を、常用労働者が100人を超える中小企業に拡大 |
■「障害者雇用率制度」とは?
企業に対し、法で定めた一定割合の障害者雇用を義務づける制度であり、雇用する常用労働者に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるようにします。
■常用労働者とは
- 雇用契約の形式の如何を問わず、期間の定めなく雇用されている労働者
- 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
- 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
- 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人としてカウントします。
■障害者数のカウントの方法
法定雇用率の算定における障害者数のカウントの仕方は、労働時間数や障害の重さによって異なります。
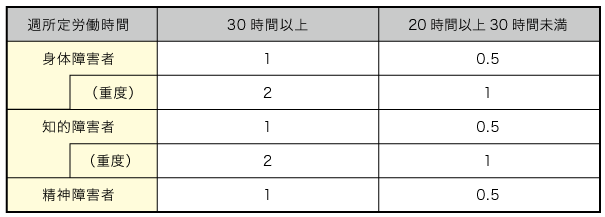
■これからの障害者雇用とは
下記の計算式を見てください。
一般民間企業における雇用率設定基準(以下の算定式による割合を基準として設定。)
法定雇用率= 身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数
+失業している身体障害者及び知的障害者の数
常用労働者数 + 失業者数
法定雇用率の算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加【施行期日 平成30年4月1日】されることが決定しています。
つまり
【法定雇用率の算定式】
となるわけです。
平成30年には、精神障害者も雇用しなければならないと勘違いしている企業が数多くいます。精神障害者を雇用しなければならないのではありません。法定雇用率の計算式に精神障害者が加わるということです。つまり、それは分子の数字が増えるため、法定雇用率が大幅に上昇するということです。
障害者法定雇用率が大幅に上昇すると、未達成企業も増えますし、納付金の額が急激に上昇してしまい経営を圧迫することも考えられます。そのため、激変緩和措置の内容も公表されています。
- ○現状 平成25年4月1日~平成30年3月31日
-
身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率(2.0%)
- ○平成30年4月1日~平成35年3月31日
- 身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と
身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率
- ○平成35年4月1日以降
- 身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率
平成25年に法定雇用率が2.0%に上がったことにより、50人以上規模の企業に障害者の雇用義務が発生することになりました。
以前は、300人未満の企業は納付金の免除があったため、300人規模の企業は障害者雇用には意識が薄く消極的でしたが、平成25年には200人以上、平成27年には100人以上の企業規模が納付金制度の対象となりました。
法定雇用率が上がり、7万社を超える法定雇用率対象企業が採用活動を行うことになり、今は、障害者雇用の採用現場はより一層の超売り手市場となっています。
しかし、この度の採用拡大の裏で多くの早期退職者も出ることが予想されます。採用することは簡単にできても継続して雇用することは難しいのです。
■企業に求めたい気づき
「障害者雇用は企業の社会的責任である」とし、企業に対し、従業員の一定割合を障害者とするよう義務づけているのが、「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。
障害者雇用への取り組みは、「法律が定めているから」と考える企業から、「必要な戦力として」と考える企業までいろいろなケースがあります。
日本は少子高齢化が進み、労働力人口の減少もあるため、企業存続には人員確保が必要となります。その人材確保の選択肢のひとつとして障害者雇用があります。
「理解があり、少し配慮してもらえるならば働いてみたい」と願う障害者は数多くいます。
○障害ゆえにできないことは何か?
○少しの配慮があればできることは何か?そのできることの中で得意なことは何か?
これを本人も、企業も知ることが必要です。残念ながら、自分の得意なものに気づいていない障害者も数多くいます。
障害者には、先天的に障害を持っているケースと人生の半ばで病気や事故により障害を負ったケースがあります。同一の障害名、同一の等級であったとしても、個々人の状態は違います。一人一人と向き合うことが必要です。
■丁寧に着実に
障害者雇用の実績が乏しい企業ほど「どんな仕事をしてもらったらいいのかわからない。」「面倒をみる余裕がない。」という意見があります。
一度採用したけれども上手くいかなかった場合、「もう懲りた。」と採用をあきらめるケースもあります。障害者の雇用については、急いで数を追いすぎず、とにかく丁寧に進めていくことが重要です。企業と障害者の方のニーズを汲み取ることが最優先なのですが、まずは求職者の障害特性を理解し、それに応じた雇用制度や配置を柔軟に行うこと。そして、就業後のフォロー体制を確立することが不可欠です。急いで雇用率を上げることより丁寧に着実に雇用を進めることが大切なのではないでしょうか。
雇用される障害者、雇用する事業主、その中を取り持つ支援機関、この3つに接点を持つことができるのが社会保険労務士です。
障害者雇用の責任は承知しているけれど、なかなか一歩が踏み出せない企業様は一度、ご相談ください。
医療機関、福祉施設の方へ
- 労務管理に関する法令の内容がよくわからない
- 勤務シフトの見直しをして残業を減らしたい
- 子どもを産んでも仕事を続けることができる職場にしたい
- 休みがなかなかとれないという悩みを解消したい
- 就業規則の内容が実態とあわない などなど
医療機関等でも、労働者を雇用し、その労働の対価として賃金を支払うという「労働契約」を締結しており、そこには、労働基準法を始めとする様々な規制・制約を受けるのも他の業種と変わりありません。
しかし、医療法の人員配置基準、資格者集団、男女の比率、労働需給のアンバランスと言った、医療機関の特殊性が存在します。
医療労務コンサルタントの認定を受けた西岡慶子は、
環境改善のお手伝いをします。
当直、夜勤・交代制勤務や長時間労働など激しい勤務環境にある医師や看護職員、介護職員等の方々が健康で安心して働くことができる環境改善を、人材が確保しやすくなるような好事例研究をもとに個別支援業務、相談対応業務、情報収集等業務等を行い、貴院・貴施設にあった改善をお手伝いしていますので、お気軽にご相談ください。
■ 医療労務コンサルタントとは
病院に勤める医者・看護師等医療従事者の勤務時間の見直しや、休日取得・宿直勤務や、メンタルヘルス問題など主に 病院の労務管理を適正に運用するために、厚生労働省、日本医師会、日本看護協会と社会保険労務士会が一体となって取り組んでいます。
医療労務コンサルタントの認定は、厚労省から委託された全国社会保険労務士会連合会が、各都道府県社労士会に委託し実施する「医療労務コンサルタントの研修」を修了した社会保険労務士に付与されます。
帰国する外国人のための支払った年金の払い戻し
帰国する外国人のみなさん!「支払った年金の払い戻し」ができます!
日本では企業に雇われて働けば、国籍に関係なく年金を納める義務があり、外国人の皆さんも年金を納めています。
日本に永住せず帰国する人には、支払った年金を「脱退一時金」として払い戻す制度が用意されています。
 脱退一時金とは
脱退一時金とは
日本にいる間に年金を支払っていた外国人が、日本から出国した場合、 本国から請求すれば、払い戻されるものです。 あなたには「脱退一時金」が支給される権利があることを知ってください。
■ 脱退一時金の請求の実情
- 多くの外国人が、納めた年金を「脱退一時金」として払い戻されることを知りません。
- 帰国後、請求方法がわからず、あきらめた方が多くいます。
- 帰国後、請求を失敗したまま、困っている方が多くいます。
(書類が返戻される理由は15以上あります。) - 帰国後、2年以内に請求しなければ、もらえるはずの「脱退一時金」が無駄になります。
■ 日本国外から請求する場合の問題点
請求期間は長期に及ぶため、転居やあなたが書いた住所にあいまいな部分などがあったりすると郵便事故が起こる可能性もあります。
不備があった場合は日本の年金当局に問い合わせますが、日本語対応のため、あなたは日本語が十分に話せ、専門用語を理解する必要があります。
記載事項は、正しいものでないと受け付けられません。そのため訂正などがあると書類は返送され、送付回数が増えると郵便事故が多くなります。
多くの書類を、費用を自己負担し、間違いなく日本の年金当局へ送付する必要があります。
脱退一時金の請求の失敗は、あなたたち外国人の認識と日本の役所の認識が違っていているからです。それが、書類の不備の大部分の原因となっています。
請求に失敗すると、確認の書類のやり取りで、長い年月を無駄にしたり、さらには請求期限切れとなってしまいます。脱退一時金を請求できる二年間という期間は、海外から自分で請求するリスクを考えると、決して長い期間ではありません。
■ 脱退一時金が請求できる方
帰国する外国人なら誰でも請求できるわけではありません。下記のすべての要件を満たす必要があります。
- 日本国籍を持っていないこと
- 厚生年金または国民年金の加入期間が6ヵ月以上あること
- 日本に住所がないこと
- 老齢基礎年金、老齢厚生年金などの年金の受給権を満たしていないこと
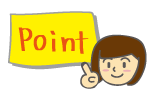
- 国民年金の被保険者でないこと
- 障害年金などの年金を受ける権利を持っていない
- 市区町村へ転出届を提出していること
■ 払い戻される「脱退一時金」の額
脱退一時金の支給額は、国民年金と厚生年金で計算式が異なります。また、その外国人がもらっていた給料の金額(厚生年金)、支払っていた国民年金保険料の額、支払っていた時期ごとの保険料率など、細かい様々な数字を掛け合わせて計算します。ですので、人によって支給される金額が違います。
■ 脱退一時金を請求する場合の注意点
- 母国が、社会保障協定(年金の二重加入・二重負担防止、年金加入期間の通算)を締結している場合、脱退一時金を日本国から支給された場合、その期間は、母国の社会保障協定の年金加入期間として通算されなくなります。
したがって、日本と母国が社会保障協定を締結している国籍の方は、脱退一時金を日本国から受け取るメリットと、日本での年金加入期間を以降持ち越せなくなるデメリットとをよく比較して判断しましょう。
私たちが請求代行すれば、
- 私たちは「脱退一時金」の請求に係る手続きを迅速かつ正確に請求代行することができます
- 万が一書類に不備がある場合は、私たちが日本の当局と対応して問題解決いたします
- 私たちは、できる限り日本国内にいる間に書類をそろえるよう努力し、書類不備のリスクを最小限にします
- 私たちは、年金当局からの重要な情報をあなたに伝える役割を果たし、わかりにくい情報を円滑にお伝えします
- 脱退一時金の請求は、実際に支給されるまで長期に渡るため事前のお約束事があります。
- 必要な書類、揃え方・コツをわかりやすくご説明します。
- 必ずメールで件名を『外国人の年金の相談』として、帰国前にお問い合わせください。
ここに記載される情報は全て一般的な内容説明です。法律に改正があったり、審査基準に変更などがあった場合はこの限りではありません。情報の利用においての責任は利用者に帰属します。詳しくは日本年金機構のサイトでご確認ください。